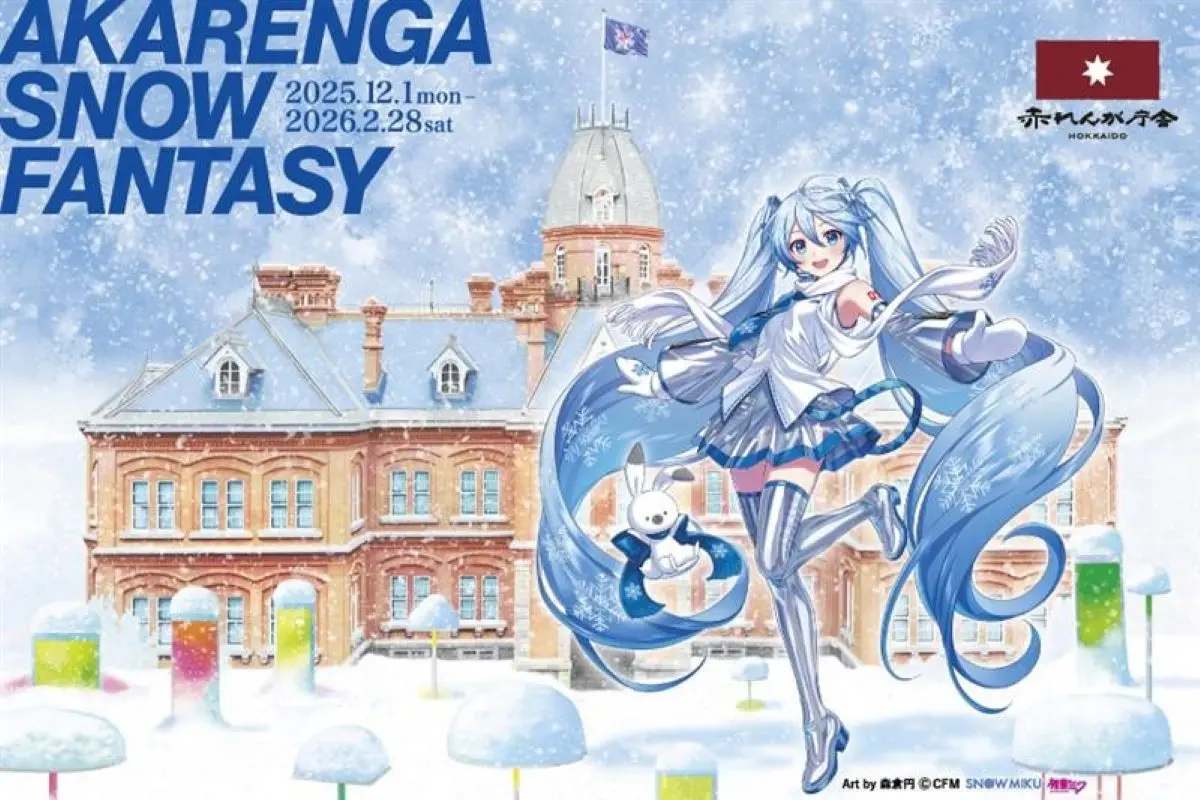北海道でワイナリーの数が最も多い余市町で、余市産ワインや余市産ブドウを使ったワインを味わう「第29回ワインを楽しむ会」が2月22日、余市町公民館で開かれ、TripEat北海道編集部のメンバーと参加しました。17のワイナリーが59銘柄のワインを出品し、町民や愛好者らが余市の風土が育んだ美酒を堪能しました。
ワインもオードブルもフリー

余市町では1970年代からワイン用ブドウの栽培が始まり、77年に余市ワインが操業を始めました。84年にサッポロワインなどが町内の農家とブドウ栽培の契約を交わしたのをきっかけに、道内外のワイナリーが町内の農家と栽培契約を結ぶようになりました。2010年に初めて、小規模ワイナリーが設立され、近年はブドウ栽培の新規就農やワイナリー開設が相次いでいます。
ワインを楽しむ会はコロナ禍での休止を経て、昨年5年ぶりに開かれ、今回で29回目となりました。事前予約制のチケット250枚は完売です。参加料は5500円で、オードブル、出品ワインはすべてフリーです。


入り口でウェルカムワインの入ったグラスを受け取ります。ウェルカムワインはサッポロビールの「グランポレール 余市ぶどうのスパークリング」。余市町の6戸の契約農家が栽培しているケルナーとバッカス、ミュラートゥルガウの3種類のブドウをブレンドした微発泡の白ワインで、すっきりと飲みやすい味わいです。余市町と仁木町を中心に、北海道産ワインの豊富な品ぞろえで知られる町内の酒店「中根酒店」店主で、ワインアドバイザーの資格を持つ中根賢志さんが、サーブしてくれました。

会場にはテーブルが並び、余市町内に2021年にオープンしたイタリアン「Mare Blue(マーレブルー)」のオーナーシェフ大岩聖史さんが腕を振るったオードブルが置かれています。余市産北島豚肩ロース肉赤ワインみそソースや積丹産真イカのマリネ、余市・村上農園の平飼い卵のフィナンシェなど、地元産の食材もふんだんに使った、ワインに合うフードが盛り込まれています。


斉藤啓輔町長が「会場はあふれんばかりの人です。本州から来てくれた人もおり、町内のホテルはいっぱいで、経済効果も大きい。ワインのつくり手のみなさんのおかげです」とあいさつ。「余市のワインに乾杯!」という斉藤町長の音頭でグラスを合わせました。
個性豊かなワインが続々、希少銘柄も

会場の一番前のテーブルに陣取っていたところ、目の前がドメーヌ・タカヒコのブースでした。まずはここで1杯。いずれも赤の「ヨイチ・ノボリ パストゥグラン2023」と「ヨイチ・ノボリ O-Lie(オーリー) 2022」があり、パストゥグランをお願いすると、代表の曽我貴彦さん自ら、サーブしてくれました。曽我さんが「最低3年は置いて飲んで」と言う通り、3年は経っているものの、さらにもう少し、寝かせてもいいのかもしれません。とはいえ、もちろん香りも味も絶品です。


ドメーヌ・アツシスズキには赤「トモルージュ キュベ18 2022」とオレンジ「日暮れの雫と茜空 橙 2023」がありました。トモルージュはツヴァイゲルト100%でどっしりめ、橙は生産本数わずか800本と希少なものです。
山田堂「Yoichi Rose Pinot Noir 2023」はロゼですが、色はピンクというより淡く色付く程度。味も甘みは抑えめで、すっきりと飲みやすい1杯です。


モンガク谷ワイナリーは、いずれも2023年の白「栃」「楢」「栢」とロゼ「薄紅桧」の4銘柄を出品。フラッグシップの「栃 tochi 2023」をいただきます。木原茂明さん夫妻がサーブしてくれました。ピノノワールを主体に7種類のブドウを混ぜており、オレンジがかった黄金色。辛口で、心地よい苦みが特徴です。


白の残り2つも飲み比べてみましょう。「楢2023」は世界でも希少品種のピノタージュ主体。フローラルで、ライチのような香りがあり、ほのかな苦みとスパイシーさが感じられます。「栢2023」はシャルドネ主体で、モンガク谷では唯一の白ブドウを主体にしたワイン。ややにごりがあり、楢に比べて少し濃い黄金色で、柔らかな口当たりとミネラル感、うっすらと苦みもあります。モンガク谷は複数のブドウを混ぜたフィールドブレンド(混醸)で、木原さんは「それぞれブドウの良さや特徴を引き立て合い、補い合う、多様性と調和のワインです」と話します。


赤、白、オレンジの3銘柄を出品していたミソノヴィンヤードでは、白「シャルドネ2023」を選びました。町内の相馬ファームのブドウを買い取ったもので、製造本数はわずか173本。この年は鳥の食害がひどく、相馬ファームでは収穫量が前年の半分程度にとどまったそう。いつも以上に選果を徹底し、きれいなブドウのみでつくりました。果実味のあるさわやかな香りに加え、厚みのある味わいです。
ドメーヌ・ユイでは白「A4 シャルドネ2023」をいただきます。しっかり熟し、糖度を上げたシャルドネを使っており、ボリューム感のあるまろやかな飲み心地。樽発酵、樽熟成させていることから、バターのようなまろみのある香りも感じます。赤「A2 ピノノワール2023」もちょっと味見しましたが、しっかりとした色合いに似合わず、香りが華やかでフルーティーなワインでした。


キャメルファームでは白泡「バッカスエクストラドライ2022」を、編集部スタッフは赤「ピノ・ノワール フジモトヴィンヤード2022」を注いでもらいました。バッカスは発泡感が心地よく、すっきりとしたきれいな酸がありながら、うまみもあります。ピノ・ノワールは一口目にほのかに甘みがあり、柔らかい渋みも感じます。


最初にいただいたドメーヌ・タカヒコのブースには、この間、ずっと長い行列ができていましたが、ふと見ると空いています。それなら、最初に飲まなかったオーリーをいただきましょう。オーリーは生産本数400本。フランス語で「おり」を意味する「Lie(リー)」から名付けられた通り、おりとともに熟成させたやや濁りのあるワインです。余市町のワイナリーやヴィンヤードを巡りながら、ワインを味わう夏のイベント「ラフェト・デ・ヴィニュロン・ア・ヨイチ(農園感謝祭)」で飲んで以来、オーリーは私の中では、フラッグシップのナナツモリと甲乙つけがたい存在です。
ココ・ファーム・ワイナリーは、栃木県足利市のワイナリーで、余市町内で生産したブドウを使ったワインをつくっています。「こことあるシリーズ2019 ツヴァイゲルト」は小西農園と中川農園のブドウを使用し、やや渋みのあるしっかりめの骨格のワインに仕上がっています。


リタファーム&ワイナリーでは、赤「風のヴィンヤード ピノ・ノワール2021」をいただきます。しっかりした果実味と、心地よい渋みがありますが、全体的に優しい雰囲気で、飲みやすいワインです。白「風のヴィンヤード ソーヴィニヨン・ブラン2020」も飲んでみます。ややにごりがあり、まろやかなかんきつの味と香り、かすかな苦みもあり、複雑な味わいです。


Yoka Wineryの「余香(よか)」は自社栽培のブドウを、「余珀(よはく)」は買いブドウを使ったシリーズ。せっかくなので、自社ブドウの白「余香 シャルドネ2023」をいただきましょう。色は淡めで、グレープフルーツのようなかんきつ系の香りがします。30年以上も耕作放棄された畑で、石や岩と格闘しながらブドウを植え、2018年から22年までは岩見沢市の10Rワイナリーに委託醸造し、この2023年が初めて自社の設備で醸造したヴィンテージです。
ニッカ余市ヴィンヤードはニッカウヰスキーの子会社で、2018年から「NYV」の銘柄でワインをリリースしています。「ケルナー2023」はフルーティーですっきりした酸が感じられます。
ワインが当たる抽選会で大盛り上がり


これで、大手のワイナリー6社を除く11ワイナリーのワインを制覇しました。イベントも終盤、会場では抽選会が始まり、大盛り上がりです。実行委員会代表で弘津ヴィンヤードの弘津雄一さんと、札幌の「ワインカフェ ヴェレゾン」経営の荒井早百合さんが司会を務め、次々と番号が読み上げられます。くじ運はない方なのですが、この日は幸運の女神が気まぐれを起こしたのか、サッポロビール・グランポレールの「余市バッカス2019」が当たりました。手渡した当たりの番号札を手に、「当選おめでとう。良かったね!」と満面の笑顔をくれた荒井さんに見送られて、幸せな気持ちで会場を後にしました。